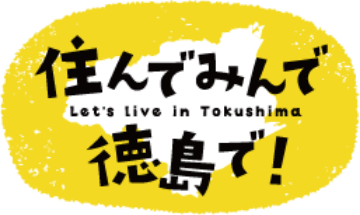阿波市地域おこし協力隊を2021年3月に退任した井本加奈子さん(愛知県半田市出身)にお話を伺いました!(2025年3月取材)
Q1協力隊になる前は何をしていましたか?
山形県の大学と大学院を卒業後、兵庫県の食用油を作り販売する会社で8年間勤めていました。会社員時代は工場の設備管理が仕事でした。
Q2なぜ阿波市の地域おこし協力隊になったのですか?
設備管理の仕事は工事業者さんと打ち合わせをして工事をしてもらうということが多く「自分の体を動かして働きたい」と少し物足りない気持ちがありました。また山登りが趣味で自然の中にいるときがとても幸せで、次第に「農業をしてみたい」という想いが育っていきました。はじめは農業関係の求人を関西付近で探していたのですが、探していた時に出会った方に移住も視野に入れて探すといいとアドバイスをいただいたので、大阪ふるさと暮らし情報センターを訪れてみました。そこで地域おこし協力隊という制度を知り、その中で阿波市の募集を見つけ、ぶどう農家と養蜂家の下で勉強するという内容が私のやりたいことに合致していると思い応募しました。
Q3実際に阿波市に移住して暮らしてみていかがですか?
阿波市に来る前は大阪の吹田市に住んでいたのですが、通勤時の人混みや街の騒がしさに疲れていました。だから阿波市に移住してきて、静かで星空がきれいなところに心癒されました。住み慣れた今は農業が身近で、そんなに田舎過ぎず都会と近すぎず遠すぎずちょうどいい距離に位置していて住みやすいところだなと感じています。また、私は本を読むのが好きなので図書館が充実しているところも気に入っています。
Q4現役の時はどんな活動をしていましたか?
募集をみた時には、ぶどう農家を目指すか養蜂家を目指すか悩んだのですが、事前に農家さんの話を聞くことができ養蜂をしたいと決断しました。活動は地元の養蜂家さんの下で1から養蜂を学ぶことでした。養蜂家さんのミツバチの世話を一緒にさせてもらいながらミツバチの管理方法を学びました。また1年目に「自分なりに育ててみなさい」と巣箱を1つとミツバチの群れを1群いただきました。独立を意識しはじめた2年目は1年目に頂いたミツバチを15群、3年目は50群まで増やし着々と独立の準備を行いました。その他の準備としてはお世話になっている養蜂家さんや市役所の方にも協力していただきながら新しい住居や巣箱を置く蜂場を探したり、事業計画をたてたりしました。
Q5活動中気を付けていたことはありますか?
教えてくださった養蜂家の方が丁寧に優しく教えてくれる方だったので、それに甘えないように気を付けて、3年後の独立にむけて準備を進めていきました。
Q6これからやっていきたいことは何ですか?
ミツバチの行動範囲は巣箱から2から4キロメートルなので、その範囲にある花の蜜を集めてできるハチミツはまさに巣箱周辺の環境が味にダイレクトに反映されていると言えます。また、ハチミツは1年に2から3回春と秋に採蜜できるのですが、春と秋では咲いている花が違うのでハチミツの味や色が違います。養蜂家の中では味を安定させるためブレンドして商品にする方も多いのですが、私は季節ごとの阿波市の環境が育んだ味の違いを楽しんでいただきたいので採蜜日ごとに充填して採蜜日を商品に記載しています。そんな商品のこだわりを守りながらこれからも養蜂を続けていきたいです。また、ハチミツの加工品を作ったり蜜源植物を育てたり新しいことにも少しずつ挑戦したいです。そして、忙しい季節が始まると1つの巣箱に対して9日の間隔で巣箱を見に行き、それと同時に採蜜や借りている蜂場の草刈りなどを行い、夜は蜂蜜の充填…といっぱいいっぱいになってしまうのでもっと効率的かつ計画的に作業を行い田舎暮らしを楽しみたいです。時間ができればせっかく持っている畑があるので作物を育てることができたらと思います。
<井本養蜂園の商品>
Q7徳島県の魅力は何だと思いますか?
阿波市に住んでいるから感じていることかもしれませんが、移住者に対して壁を感じない、人を受け入れる度量のある人が多いところが素敵だなと思います。県外の養蜂家の中には蜂を扱っているのであまり歓迎されないという話も聞くことがあるのですが、ありがたいことに私は逆に近所の人が商品を買ってくださったり人を紹介してくださったりと、応援してくれていて住みやすいなと感じています。
<井本さんが阿波市に来てすぐのころ楽園のような景色が日常にあることに驚いた吉野川沿いの阿波市の風景>